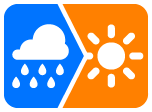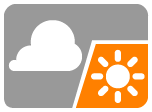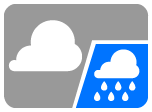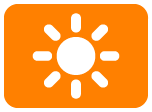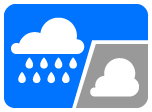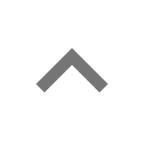まれな疾患から国民病に
スギなどの植物の花粉で起きるアレルギー疾患の花粉症は、「欧米では200年以上前からhay fever(枯草熱)として、牧草花粉症が知られていましたが、日本では1964年に初めて報告され、1980年代に国の問題として対策が取られるようになりました。
しかし、1998年には約16%、そして現在では約40%(※)と、有病率は急速に高くなり、一般の人にもよく知られる疾患となりました」(岸川先生)
※「鼻アレルギー診療ガイドライン2024年版」より
しかし、1998年には約16%、そして現在では約40%(※)と、有病率は急速に高くなり、一般の人にもよく知られる疾患となりました」(岸川先生)
※「鼻アレルギー診療ガイドライン2024年版」より

岸川先生らは、1987年から宮城県仙台市から熊本県熊本市にわたる全国各地の施設の協力のもと空中花粉調査を行い、その中の9施設で20年以上の長期調査が行われました。
「各施設の屋上に花粉捕集器を設置し、ワセリンをうすく塗布したスライドグラスを固定し、スライドグラスに自然落下する花粉を24時間毎に集め調査しました」(岸川先生)
花粉症の原因となる花粉は、よく知られるスギなどヒノキ科のほか、カバノキ科、イネ科、キク科、ブナ科などさまざまですが、岸川先生は重要なアレルゲンであるヒノキ科のスギとその他のヒノキ科について、気候変動による影響を調べました。
「各施設の屋上に花粉捕集器を設置し、ワセリンをうすく塗布したスライドグラスを固定し、スライドグラスに自然落下する花粉を24時間毎に集め調査しました」(岸川先生)
花粉症の原因となる花粉は、よく知られるスギなどヒノキ科のほか、カバノキ科、イネ科、キク科、ブナ科などさまざまですが、岸川先生は重要なアレルゲンであるヒノキ科のスギとその他のヒノキ科について、気候変動による影響を調べました。
花粉飛散量と天気に密接な関係が
植物の生育には気温や日照時間、降水量など気候の影響が大きいものですが、空中を飛散する花粉の量も同じく影響を受けます。明らかなのが夏と冬の天気です。
「観測地点は日本各地にありますが、地域によって花粉量は異なり、また各地の花粉量は年によって大きく変動します。
スギ、ヒノキ科は夏に花芽(はなめ)が成長するため、夏の天気の影響が翌年の花粉に現れます。影響が強い条件は、気温、日照時間、湿度です。
私たちの観測でも、夏(6〜8月)の平均気温と翌年の花粉量には相関関係があり、特に7月が最も強く関係していました。
また、夏の総日照時間のうち、7月と8月は花粉量と強く関わっていて、総日照時間が長くなるほど、花粉量は増加しました。一方で7月の月平均湿度が低いほど、花粉粒数が多くなることも分かりました。
つまり、夏の気温が高く日照時間が長く、雨が少なめで湿度が低いほど翌年の春の花粉の量は増加するということです。
また、冬の平均気温が高くなるほど、花粉の飛散開始日が早まるという関係がみられました」(岸川先生)
「観測地点は日本各地にありますが、地域によって花粉量は異なり、また各地の花粉量は年によって大きく変動します。
スギ、ヒノキ科は夏に花芽(はなめ)が成長するため、夏の天気の影響が翌年の花粉に現れます。影響が強い条件は、気温、日照時間、湿度です。
私たちの観測でも、夏(6〜8月)の平均気温と翌年の花粉量には相関関係があり、特に7月が最も強く関係していました。
また、夏の総日照時間のうち、7月と8月は花粉量と強く関わっていて、総日照時間が長くなるほど、花粉量は増加しました。一方で7月の月平均湿度が低いほど、花粉粒数が多くなることも分かりました。
つまり、夏の気温が高く日照時間が長く、雨が少なめで湿度が低いほど翌年の春の花粉の量は増加するということです。
また、冬の平均気温が高くなるほど、花粉の飛散開始日が早まるという関係がみられました」(岸川先生)
花粉飛散量は緩やかに増加
気候変動は花粉の飛散にどのように影響しているのでしょうか。

「1986年から2020年まで全国9地点のスギとヒノキ科の花粉で検証しました。なお、調査期間中9地点すべてで月平均気温は上昇傾向にありました。
各地点とも年によって花粉量は大きく変わっています。年によって暖かい年や寒い年があるので翌年の花粉量もそれに応じて変動しています。しかし、花粉量は点線で示されるように過去30年間で緩やかな増加傾向にあるといえます」(岸川先生)
花粉の飛散開始日についても変化がありました。
各地点とも年によって花粉量は大きく変わっています。年によって暖かい年や寒い年があるので翌年の花粉量もそれに応じて変動しています。しかし、花粉量は点線で示されるように過去30年間で緩やかな増加傾向にあるといえます」(岸川先生)
花粉の飛散開始日についても変化がありました。

「スギとヒノキ科の花粉は1〜2月に飛散し始めますが、花粉症の治療のためには飛散開始日をできるだけ正確に予想することが重要です。
グラフは1月と2月の平均気温との相関を示しており、冬の平均気温が高いと花粉の飛散開始日が早まるという関係があります。
調査では、飛散開始日は北日本(仙台、新潟)、北陸(富山)で早くなり、関東(相模原)、東海(浜松)、近畿(津、和歌山)で遅くなっています。このような地域ごとの変化により、花粉の飛散は徐々に日本全国で同じ時期に始まるようになってきています」(岸川先生)
グラフは1月と2月の平均気温との相関を示しており、冬の平均気温が高いと花粉の飛散開始日が早まるという関係があります。
調査では、飛散開始日は北日本(仙台、新潟)、北陸(富山)で早くなり、関東(相模原)、東海(浜松)、近畿(津、和歌山)で遅くなっています。このような地域ごとの変化により、花粉の飛散は徐々に日本全国で同じ時期に始まるようになってきています」(岸川先生)
温暖化で花粉症がひどくなる?
気候変動による地球温暖化の影響で、花粉症はこれから悪化すると考えられるのでしょうか。
「日本の花粉症患者数は顕著に増加しています。日本ではスギやヒノキが特に戦後に多く植林されており、人口の多い関東地方や東海地方に花粉が多いことも問題です。
飛散する花粉量の変化には植林面積や樹齢などの要因もあります。しかし、35年にわたる観察から、花粉症患者の増加の理由として気候変動がスギやヒノキ科の花粉量の増加と花粉飛散開始時期に影響したことが挙げられます。花粉量が増えたり、飛散する期間が変わることで、アレルゲンへの暴露期間に影響するからです。
北米でのブタクサの花粉シーズンの延長や、ブタクサが外来植物としてヨーロッパに拡散するリスクなど、欧米でも気候変動が及ぼす影響が報告されています。
日本でも近年は秋に飛散するスギ花粉が観測されています。今後もさらなる花粉情報を収集し、検討していく必要があるでしょう」(岸川先生)
昨年は、気候変動により熱中症や感染症のリスクが高まることが注目されましたが、花粉症などへの影響も指摘されているということですね。
ウェザーニュースでは、気象情報会社の立場から地球温暖化対策に取り組むとともに、さまざまな情報をわかりやすく解説し、みなさんと一緒に地球の未来を考えていきます。まずは気候変動について知るところから、一緒に取り組んでいきましょう。
» ウェザーニュース 花粉観測状況・飛散予想
» 【気候変動特集】ウェザーニュースと考える地球の未来
» お天気ニュース記事一覧をアプリで見る
参考資料
環境省「花粉症環境保健マニュアル2022」、「我が国のヒノキ科花粉における気候変動の影響」(岸川禮子ほか、日本花粉学会会誌22023 69(1))、「花粉症―花粉症は全身疾患―」(岸川禮子、日本耳鼻咽喉科免疫アレルギー感染症学会誌2022 2(4))
「日本の花粉症患者数は顕著に増加しています。日本ではスギやヒノキが特に戦後に多く植林されており、人口の多い関東地方や東海地方に花粉が多いことも問題です。
飛散する花粉量の変化には植林面積や樹齢などの要因もあります。しかし、35年にわたる観察から、花粉症患者の増加の理由として気候変動がスギやヒノキ科の花粉量の増加と花粉飛散開始時期に影響したことが挙げられます。花粉量が増えたり、飛散する期間が変わることで、アレルゲンへの暴露期間に影響するからです。
北米でのブタクサの花粉シーズンの延長や、ブタクサが外来植物としてヨーロッパに拡散するリスクなど、欧米でも気候変動が及ぼす影響が報告されています。
日本でも近年は秋に飛散するスギ花粉が観測されています。今後もさらなる花粉情報を収集し、検討していく必要があるでしょう」(岸川先生)
昨年は、気候変動により熱中症や感染症のリスクが高まることが注目されましたが、花粉症などへの影響も指摘されているということですね。
ウェザーニュースでは、気象情報会社の立場から地球温暖化対策に取り組むとともに、さまざまな情報をわかりやすく解説し、みなさんと一緒に地球の未来を考えていきます。まずは気候変動について知るところから、一緒に取り組んでいきましょう。
» ウェザーニュース 花粉観測状況・飛散予想
» 【気候変動特集】ウェザーニュースと考える地球の未来
» お天気ニュース記事一覧をアプリで見る
参考資料
環境省「花粉症環境保健マニュアル2022」、「我が国のヒノキ科花粉における気候変動の影響」(岸川禮子ほか、日本花粉学会会誌22023 69(1))、「花粉症―花粉症は全身疾患―」(岸川禮子、日本耳鼻咽喉科免疫アレルギー感染症学会誌2022 2(4))