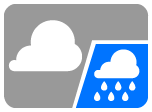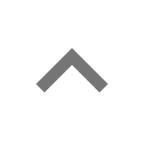小豆の栄養成分と健康効果
小豆の旬は、10月〜2月です。赤飯やお汁粉だけでなく、冬至の日に小豆のお粥を食べる冬至粥や、小正月に健康を祈って小豆粥を食べるなど、行事食に使われてきました。
小豆が人々にとって大切な食材だったのには理由があるようです。
「中国や日本では、小豆の赤色は生命を象徴する色であり、邪気を払うとして珍重されてきました。
中国最古の薬物書『神農本草経(しんのうほんぞうきょう)』にも記載され、小豆の煮汁が解毒剤として使われたとされています。漢方では、赤小豆(せきしょうず)として解毒、排膿、利尿によいとされています。
小豆にはサポニンなどのポリフェノールやカリウム、食物繊維などが含まれています。
サポニンは小豆の苦味成分ですが、抗酸化作用で体内の活性酸素を抑制するほか、血流を改善して冷え性によく、血糖値の上昇を抑えたり脂肪の蓄積を改善するとされています。余分な水分を流して、むくみ解消にも役立ちます。
カリウムはミネラルの一種で、体内の余分なナトリウムを排出したり、利尿作用によりむくみを解消してくれます。
食物繊維はしっかり摂ることで腸内環境を改善して善玉菌を増やし、便秘や肌荒れの解消、体内の老廃物の排出などに役立ちます。
小豆はとても健康効果の高い食材なので、ふだんから食事に取り入れるのがおすすめです」(石原先生)
小豆が人々にとって大切な食材だったのには理由があるようです。
「中国や日本では、小豆の赤色は生命を象徴する色であり、邪気を払うとして珍重されてきました。
中国最古の薬物書『神農本草経(しんのうほんぞうきょう)』にも記載され、小豆の煮汁が解毒剤として使われたとされています。漢方では、赤小豆(せきしょうず)として解毒、排膿、利尿によいとされています。
小豆にはサポニンなどのポリフェノールやカリウム、食物繊維などが含まれています。
サポニンは小豆の苦味成分ですが、抗酸化作用で体内の活性酸素を抑制するほか、血流を改善して冷え性によく、血糖値の上昇を抑えたり脂肪の蓄積を改善するとされています。余分な水分を流して、むくみ解消にも役立ちます。
カリウムはミネラルの一種で、体内の余分なナトリウムを排出したり、利尿作用によりむくみを解消してくれます。
食物繊維はしっかり摂ることで腸内環境を改善して善玉菌を増やし、便秘や肌荒れの解消、体内の老廃物の排出などに役立ちます。
小豆はとても健康効果の高い食材なので、ふだんから食事に取り入れるのがおすすめです」(石原先生)
小豆を使ったお手軽メニュー2種
小豆というと餡子や赤飯などが思い浮かびますが、実はさまざまな料理に活用できます。今回は、なかでも簡単にいつもの食事にプラスできる、石原先生おすすめの「煮小豆」と「小豆水」について教えていただきましょう。

▼「煮小豆」の作り方
(1)乾燥小豆300gをさっと水洗いして、たっぷりの水とともに鍋に入れ、火にかける
(2)煮立ったら、一度ザルにあけて煮汁を捨てる
(3)小豆をさっと水洗いして鍋に戻し、4〜5倍の水を加えて再び火にかける
(4)煮立ったら弱火にして約15分ほどゆで、ザルにあけて小豆を取り出す
(5)小豆と約1Lの水を鍋に入れて弱火で40〜50分、アクを取りながら柔らかくなるまで煮たら、出来上がり
「一度目の煮汁を捨てることでアク抜きになります。2度目の煮汁は取っておけば、料理などに使えます。
煮小豆はそのまま食べるのはもちろん、塩や砂糖で味付けしたり、料理に加えて使いましょう。冷蔵庫保管で5日、冷凍ならば1ヵ月を目安に食べ切ります」(石原先生)

▼「小豆水」の作り方
(1)乾燥小豆大さじ2をさっと水洗いする
(2)水気をきって保温機能のある水筒に入れる
(3)さらに水筒に熱湯300mlを入れて3分置く
(4)一度湯を捨てて、再び熱湯を入れてふたをする
(5)そのまま8時間おき、小豆と小豆水にわけて出来上がり
「小豆水は、煮小豆の要領で作って取り分けてもいいですが、少量ならば水筒(ステンレスボトル)などでとても簡単に作れます。作った小豆水は1日で飲み切ってください。分けた小豆も煮小豆と同じように食べられます」(石原先生)
寒さによるダメージは、気付かぬうちに溜まってしまいます。年始から元気に過ごすためにも、小豆のパワーを活用してみませんか。
» お天気ニュースをアプリで読む