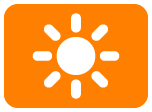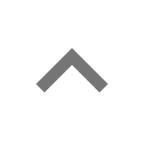飛行機雲ができる仕組み
素朴な疑問ですが、飛行機雲はどのようなもので、どうやって作られるのでしょうか。
「飛行機雲は航空機のエンジンから伸びているように見えるので、『煙(排煙)』だと思われがちですが、空に浮かぶ普通の雲と同じように氷の粒が集まってできた、れっきとした『雲』なのです。
航空機の後方に氷の粒が発生するメカニズムは、大きく2つの要因が影響しています。
1つめの要因は、航空機のエンジンの排気ガスに含まれる水分です。
排気ガスには水分が水蒸気として含まれています。飛行機が巡航状態で飛ぶ高度は1万m前後で、周囲の気温はおよそ-50℃になります。高熱をもった排気ガスには水が水蒸気として含まれていて、極低温な外気に急激に冷やされることで、水滴や氷の粒になって雲を作ります。
排気ガスには水や氷の粒の核となる粒子も含まれていて、このことも飛行機雲を発生しやすくするために一役買っています。水平飛行をしている航空機に見られる飛行機雲はこのケースです。冬の寒い日、吐いた息が白くなるのと同じ原理です。
2つめの要因は、航空機の機体が高速移動することによって生じる、空気圧の変化です。
ジェット機の翼の後ろやターボプロップ機のプロペラの先端部などは、特に周辺の気圧が低くなる特性があります。気圧が下がると空気が膨張して冷却されるため、水蒸気が氷の粒へと変わるのです」(山口剛央)
飛行機雲の発生のきっかけが水分と気圧だとして、濃かったり薄かったりという見え方の違いや、残り続ける時間に長短があったりするのはなぜなのでしょうか。
「飛行機雲がほとんど見えなかったり、発生してもすぐに消えたりしてしまうのは、飛ぶ航空機の周囲の大気の湿気が少ない場合です。飛行機雲は氷の粒でできているため、空気が乾いているとすぐに周囲の空気と混ざって温度が上がり、消えてしまうのです。
逆に、飛行機雲が現れてからいつまでも消えないときは、上空の空気が湿っているということになります」(山口剛央)
「飛行機雲は航空機のエンジンから伸びているように見えるので、『煙(排煙)』だと思われがちですが、空に浮かぶ普通の雲と同じように氷の粒が集まってできた、れっきとした『雲』なのです。
航空機の後方に氷の粒が発生するメカニズムは、大きく2つの要因が影響しています。
1つめの要因は、航空機のエンジンの排気ガスに含まれる水分です。
排気ガスには水分が水蒸気として含まれています。飛行機が巡航状態で飛ぶ高度は1万m前後で、周囲の気温はおよそ-50℃になります。高熱をもった排気ガスには水が水蒸気として含まれていて、極低温な外気に急激に冷やされることで、水滴や氷の粒になって雲を作ります。
排気ガスには水や氷の粒の核となる粒子も含まれていて、このことも飛行機雲を発生しやすくするために一役買っています。水平飛行をしている航空機に見られる飛行機雲はこのケースです。冬の寒い日、吐いた息が白くなるのと同じ原理です。
2つめの要因は、航空機の機体が高速移動することによって生じる、空気圧の変化です。
ジェット機の翼の後ろやターボプロップ機のプロペラの先端部などは、特に周辺の気圧が低くなる特性があります。気圧が下がると空気が膨張して冷却されるため、水蒸気が氷の粒へと変わるのです」(山口剛央)
飛行機雲の発生のきっかけが水分と気圧だとして、濃かったり薄かったりという見え方の違いや、残り続ける時間に長短があったりするのはなぜなのでしょうか。
「飛行機雲がほとんど見えなかったり、発生してもすぐに消えたりしてしまうのは、飛ぶ航空機の周囲の大気の湿気が少ない場合です。飛行機雲は氷の粒でできているため、空気が乾いているとすぐに周囲の空気と混ざって温度が上がり、消えてしまうのです。
逆に、飛行機雲が現れてからいつまでも消えないときは、上空の空気が湿っているということになります」(山口剛央)
飛行機雲で天気予報ができる!?

上空の空気が乾燥しているか湿っているかは、天気にも大きく影響すると思いますが。
「そのとおりです。だから飛行機雲の様子を観察することで、観天望気(自然現象などから天気の変化を予測すること)が可能になります。
『飛行機雲が長く伸びたときは雨が近い』とか、『飛行機雲がだんだん広がっていくときは天気が崩れる』という観天望気の例が挙げられます。
低気圧が接近するとき、地上よりも上空の高いところから湿った空気に覆われ始めることが多くなります。飛行機雲が長く残る場合は上空高いところの湿気が多い、つまり雨が近づいているサインととらえることができるのです」(山口剛央)
一方で、「飛行機雲がすぐに消えると晴れ」という観天望気もありますね。
「これは上空が高気圧に覆われて水蒸気が少なく、大気が安定していることを意味しています。それによって、『晴天は今後も続くだろう』と予想できるのです」(山口剛央)
「そのとおりです。だから飛行機雲の様子を観察することで、観天望気(自然現象などから天気の変化を予測すること)が可能になります。
『飛行機雲が長く伸びたときは雨が近い』とか、『飛行機雲がだんだん広がっていくときは天気が崩れる』という観天望気の例が挙げられます。
低気圧が接近するとき、地上よりも上空の高いところから湿った空気に覆われ始めることが多くなります。飛行機雲が長く残る場合は上空高いところの湿気が多い、つまり雨が近づいているサインととらえることができるのです」(山口剛央)
一方で、「飛行機雲がすぐに消えると晴れ」という観天望気もありますね。
「これは上空が高気圧に覆われて水蒸気が少なく、大気が安定していることを意味しています。それによって、『晴天は今後も続くだろう』と予想できるのです」(山口剛央)
珍しい飛行機雲も

真っ白でなく、中には虹色の珍しい飛行機雲も見られます。
「彩雲の一種です。彩雲とは、太陽の光が雲を構成する水滴の間を通り抜ける時に分光(曲げられたり散乱したり)して、雲を鮮やかな虹色に染める現象です。雲の厚みの違いが作用するため、巻積雲や高積雲が太陽の近くに広がったときによく見られます。
太陽と飛行機の高度などの位置関係によっては、太陽光が飛行機雲の氷の結晶に入って複雑に屈折することで、彩雲と同じような虹色現象が生じるケースがあります。それが『虹色の飛行機雲』の正体です」(山口剛央)
珍しい現象として、他に「消滅飛行機雲」もありますね。
「普通の飛行機雲とは逆に、広がっていた雲を航空機が通過した直後、轍(わだち)のように細長い帯状に消えてしまう現象で、『反対飛行機雲』とも呼ばれる珍しいものです。
雲の中を飛行機が通過することによって、すでに雲となっている水分がエンジンからの排気の熱によって蒸発したり、乱気流によって周囲の乾いた空気と混ざったりすることによって、航路周辺の雲だけが消散し、航路に沿って雲が切り裂かれたように見えるのです」(山口剛央)
五月晴れの日に上空を通過する航空機の姿が確認できたら、飛行機雲の様子にも注目してみてください。運がよければ、虹色の飛行機雲や消滅飛行機雲が見られるかもしれません。
>>詳しい天気をアプリで見る
「彩雲の一種です。彩雲とは、太陽の光が雲を構成する水滴の間を通り抜ける時に分光(曲げられたり散乱したり)して、雲を鮮やかな虹色に染める現象です。雲の厚みの違いが作用するため、巻積雲や高積雲が太陽の近くに広がったときによく見られます。
太陽と飛行機の高度などの位置関係によっては、太陽光が飛行機雲の氷の結晶に入って複雑に屈折することで、彩雲と同じような虹色現象が生じるケースがあります。それが『虹色の飛行機雲』の正体です」(山口剛央)
珍しい現象として、他に「消滅飛行機雲」もありますね。
「普通の飛行機雲とは逆に、広がっていた雲を航空機が通過した直後、轍(わだち)のように細長い帯状に消えてしまう現象で、『反対飛行機雲』とも呼ばれる珍しいものです。
雲の中を飛行機が通過することによって、すでに雲となっている水分がエンジンからの排気の熱によって蒸発したり、乱気流によって周囲の乾いた空気と混ざったりすることによって、航路周辺の雲だけが消散し、航路に沿って雲が切り裂かれたように見えるのです」(山口剛央)
五月晴れの日に上空を通過する航空機の姿が確認できたら、飛行機雲の様子にも注目してみてください。運がよければ、虹色の飛行機雲や消滅飛行機雲が見られるかもしれません。
>>詳しい天気をアプリで見る