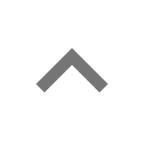美しき声の持ち主

春の暖かな日差しに包まれながら聞いていたいウグイスの声。その美しい声に耳をすますと、心が癒やされていきます。
そんなウグイスは、オオルリ、コマドリと並び、「日本三鳴鳥」に選ばれています。しかし、ウグイスだって最初から上手に鳴くことが出来るわけではありません。
まだ春本番とまではいかず、少し寒さが残る頃、「ホーホケッ?」とうまく鳴くことができないウグイスの声を聞いたことはありませんか?これは「ぐぜり鳴き」と言われています。
若いウグイスはもちろん、ベテランのウグイスだって春先はこの「ぐぜり鳴き」の状態です。しかし、何度も練習して、ようやく美しいさえずりができるようになります。
ちなみに、「ホー」は息を吸う音で「ホケキョ」がさえずりと言われています。
そんなウグイスは、オオルリ、コマドリと並び、「日本三鳴鳥」に選ばれています。しかし、ウグイスだって最初から上手に鳴くことが出来るわけではありません。
まだ春本番とまではいかず、少し寒さが残る頃、「ホーホケッ?」とうまく鳴くことができないウグイスの声を聞いたことはありませんか?これは「ぐぜり鳴き」と言われています。
若いウグイスはもちろん、ベテランのウグイスだって春先はこの「ぐぜり鳴き」の状態です。しかし、何度も練習して、ようやく美しいさえずりができるようになります。
ちなみに、「ホー」は息を吸う音で「ホケキョ」がさえずりと言われています。
鳴き声いろいろ
ウグイスの鳴き声には、以下の様な種類があります。
【谷渡り鳴き】
繁殖期のオスだけが出す鳴き声で、縄張りに天敵が近づいた時、さえずりとは違う、けたたましい鳴き声を放ちます。
【笹鳴き】
冬期のオスとメスがチャッチャッという小さな声で鳴くもの。
【地鳴き】
上記2つの鳴き声が条件付きなのに対し、地鳴きはオスとメスが一年を通して出す鳴き声。
【さえずり】
おなじみ「ホケキョ」はオスからメスへの求愛の時に出される鳴き声です。
メスのみならず、私たち人間も魅了されてしまいますよね。
このさえずりには、縄張り宣言の意味もあると言われているのですが、全く同じさえずりではなく、求愛の時と聴き比べると、もう少し低いさえずりのようです。
【谷渡り鳴き】
繁殖期のオスだけが出す鳴き声で、縄張りに天敵が近づいた時、さえずりとは違う、けたたましい鳴き声を放ちます。
【笹鳴き】
冬期のオスとメスがチャッチャッという小さな声で鳴くもの。
【地鳴き】
上記2つの鳴き声が条件付きなのに対し、地鳴きはオスとメスが一年を通して出す鳴き声。
【さえずり】
おなじみ「ホケキョ」はオスからメスへの求愛の時に出される鳴き声です。
メスのみならず、私たち人間も魅了されてしまいますよね。
このさえずりには、縄張り宣言の意味もあると言われているのですが、全く同じさえずりではなく、求愛の時と聴き比べると、もう少し低いさえずりのようです。
梅に鶯
「梅に鶯」とは、取り合わせのよい二つのもの、よく似合って調和する二つのもののたとえ。仲のよい間柄のたとえです。(引用:故事ことわざ辞典)
確かに、春を告げる梅の花にウグイスとは、非常に風流な組み合わせです。
しかし、ウグイスはあまり梅の木にはとまってくれないようです。というのも、ウグイスは花の蜜というよりは、昆虫などを捕らえて食べることが多いと言われています。「梅に鶯」って意外とレアだったんです!
昔の人たちは、梅とウグイスの組み合わせに、「春らしさ」と、珍しいこの二つの共演…というある種の「理想」を見出して、ことわざを作ったのかもしれませんね。
おさらい七十二候
1年を春夏秋冬の4つの季節に分け、それぞれをさらに6つに分けた24の期間を「二十四節気」といいます。
そしてこれをさらに初候、次候、末候の5日ずつにわけて、気象の動きや動植物の変化を知らせるのが七十二候です。
二十四節気と七十二候は、その日だけではなく、二十四節気であれば15日間、七十二候であれば5日間の期間も指しています。
次回は立春の末候、「魚上氷(うおこおりをいずる)」についてご紹介します。
» この他の気象ニュース一覧
そしてこれをさらに初候、次候、末候の5日ずつにわけて、気象の動きや動植物の変化を知らせるのが七十二候です。
二十四節気と七十二候は、その日だけではなく、二十四節気であれば15日間、七十二候であれば5日間の期間も指しています。
次回は立春の末候、「魚上氷(うおこおりをいずる)」についてご紹介します。
» この他の気象ニュース一覧