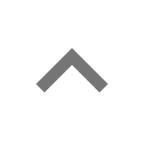車中泊した朝に倒れて亡くなる
熊本地震が発生して4日後の2016年4月18日の朝、熊本市内の自宅敷地に停めていた車で寝泊まりしていた50代の女性が車から降りたところで突然倒れ、病院に運ばれましたが死亡しました。原因はエコノミークラス症候群(急性肺血栓塞栓症)。熊本地震で最初の事例でした。
その後、同様の事例が続きました。病院に運ばれて一命を取りとめる人もいれば、残念ながら命を落とす人もいました。熊本県によると、熊本地震による死者263人のうち、エコノミークラス症候群を含む「震災関連死」はその5分の4にあたる208人にのぼります(2018年3月29日まで)。震災関連死のうち少なくとも60人は車中泊していたことがわかっています。
被災者が車中泊を続ける理由に、避難所では他人に気を使うこと、車だとすぐ逃げられること、余震で避難施設が倒壊する恐れなどをあげました。
その後、同様の事例が続きました。病院に運ばれて一命を取りとめる人もいれば、残念ながら命を落とす人もいました。熊本県によると、熊本地震による死者263人のうち、エコノミークラス症候群を含む「震災関連死」はその5分の4にあたる208人にのぼります(2018年3月29日まで)。震災関連死のうち少なくとも60人は車中泊していたことがわかっています。
被災者が車中泊を続ける理由に、避難所では他人に気を使うこと、車だとすぐ逃げられること、余震で避難施設が倒壊する恐れなどをあげました。
避難所生活でもエコノミークラス症候群
福島県立医科大学講師の高瀬信弥さん(心臓血管外科)は、「エコノミークラス症候群」医療チームとして東日本大震災の避難所を巡回して予防指導・早期発見に努めました。脚にできる血栓(血の固まり)を検査するエコーで1000人を超える被災者をスクリーニングしたところ、約10%に血栓ができていた、つまりエコノミークラス症候群を発症する可能性があったといいます。
「車中泊がエコノミークラス症候群になりやすいのは確かですが、避難所暮らしでも発症するリスクがあります。避難所ではあまり歩かず、トイレに行く回数を減らすために水分を取らないといったことが原因です」(高瀬さん)
「車中泊がエコノミークラス症候群になりやすいのは確かですが、避難所暮らしでも発症するリスクがあります。避難所ではあまり歩かず、トイレに行く回数を減らすために水分を取らないといったことが原因です」(高瀬さん)
エコノミークラス症候群を予防する3原則
エコノミークラス症候群は、窮屈な飛行機のエコノミークラスに長時間座っていた人が発症することがあることから名付けられました。しかし、脚を長時間動かさないと、床に座っていても、車に乗っていても発症します。

脚を動かさないと脚の静脈に血栓ができて、その血栓が肺血管に流れて血管を詰まらせる「肺塞栓症」を引き起こすのがエコノミークラス症候群です。
先の高瀬さんは、エコノミークラス症候群を予防する3原則をあげます。
先の高瀬さんは、エコノミークラス症候群を予防する3原則をあげます。

大地震で助かっても、避難中に心身のストレスなどで命を落とす震災関連死は「第二の被災」とも言われます。「第一の被災」を防ぐのは難しくても、「第二の被災」は免れることができます。避難生活を工夫して命を守ってください。