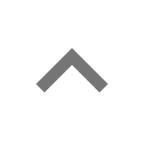強力な除雪車両で除雪する!

「線路上に積もった雪を除雪するためには、『排雪モータカー』が出動します。排雪モータカーは、モータカーの先頭にラッセル装置を取り付けたもので、線路上の雪を脇に押しのけながら進みます。現在は、在来線に50台を配備しています」(JR北海道広報部)
広報部によると、排雪モータカーを2台連結して出力性能を向上させた「ラッセルモータカー」(タイトル下の写真)は排雪モータカーより高速での作業が可能で、現在、在来線用に4編成8台が配備されているそうです。
また、排雪モータカーにロータリー装置を取り付けた「排雪モータカーロータリー」は、雪をかき寄せて、遠くへ飛ばします。北海道新幹線用に6台、在来線用には62台が配備されているといいます。
広報部によると、排雪モータカーを2台連結して出力性能を向上させた「ラッセルモータカー」(タイトル下の写真)は排雪モータカーより高速での作業が可能で、現在、在来線用に4編成8台が配備されているそうです。
また、排雪モータカーにロータリー装置を取り付けた「排雪モータカーロータリー」は、雪をかき寄せて、遠くへ飛ばします。北海道新幹線用に6台、在来線用には62台が配備されているといいます。
「ポイント不転換」の対策

「ポイント不転換」とは、鉄道のポイント(分岐器)に雪や氷塊が付着して、正常に作動しなくなることをいいます。最近では、首都圏の鉄道も電気や温水によるポイント融雪器を備えていますが、JR北海道は、より強力な装置を用意しています。
「ポイントの枕木間で、特に可動不良になりやすい部分に『ポイントマットヒーター』を敷設しています。新幹線の奥津軽いまべつ駅や札幌駅など、計252ヵ所に設置しています。
ポイントの下に空間(ピット)を設ける『ポイント融雪ピット』は、雪などを落とし、ピットの底のマットヒーターで雪を溶かす仕組みになっています。新幹線の新箱館北斗駅や旭川駅など、73ヵ所に設けられています。
『圧縮空気式除雪装置』は、ポイント転換時などに、圧縮した空気を吹き付けて雪や氷を吹き飛ばします。新幹線の新箱館北斗駅や札幌駅など、147ヵ所に設置しています」(同)
「ポイントの枕木間で、特に可動不良になりやすい部分に『ポイントマットヒーター』を敷設しています。新幹線の奥津軽いまべつ駅や札幌駅など、計252ヵ所に設置しています。
ポイントの下に空間(ピット)を設ける『ポイント融雪ピット』は、雪などを落とし、ピットの底のマットヒーターで雪を溶かす仕組みになっています。新幹線の新箱館北斗駅や旭川駅など、73ヵ所に設けられています。
『圧縮空気式除雪装置』は、ポイント転換時などに、圧縮した空気を吹き付けて雪や氷を吹き飛ばします。新幹線の新箱館北斗駅や札幌駅など、147ヵ所に設置しています」(同)
最後は人力! 1100人体制で除雪

排雪モータカーも、各種ポイント対策も、JR北海道が誇る強力な装備ですが、いよいよとなったら、人力に頼って除雪を行うそうです。
「駅構内の線路間やホーム上など、機械で除雪ができない場所は、人力に頼らざるを得ません。全道の駅構内で、1日あたり1100人の除雪作業員が昼夜を問わず除雪作業を行っています。
また、安全運転や定時運転のためには、踏切の除雪作業欠かせません。踏切が自動車の行き来によって雪で埋まると、列車が脱線するおそれがあります。踏切内で自動車が停まらないように、踏切道も除雪する必要があります。車両に付着した雪の除雪・融雪や、トンネル内のつらら落としも、人力による作業となります」(同)
「駅構内の線路間やホーム上など、機械で除雪ができない場所は、人力に頼らざるを得ません。全道の駅構内で、1日あたり1100人の除雪作業員が昼夜を問わず除雪作業を行っています。
また、安全運転や定時運転のためには、踏切の除雪作業欠かせません。踏切が自動車の行き来によって雪で埋まると、列車が脱線するおそれがあります。踏切内で自動車が停まらないように、踏切道も除雪する必要があります。車両に付着した雪の除雪・融雪や、トンネル内のつらら落としも、人力による作業となります」(同)
北海道新幹線の対策は?

最高速度260km/hで走行する新幹線では、上り列車が新青森以南の東北新幹線区間を走行すると、気温の上昇に伴って台車まわりに付着した雪が飛散して、沿線の民家や地上設備を損傷するおそれもあります。そこで、(1)線路上の雪を除雪する、(2)新青森駅で車両の着雪状況を確認する、このような対策が必須となっているそうです。
「線路上の除雪には、レール面下70mmまで除雪できる『確認車』を使用します。確認車による除雪後、さらにレール面下100mmまで除雪できる『ブラシ式除雪装置』、駅構内や本線上に積もった雪は『雪捨車』で定期的に排雪しています」(同)
新青森駅に到着した上り列車の着雪状況は、車両床下を撮影するカメラで確認して、対処が必要な際には、人力で対応しているそうです。
「線路上の除雪には、レール面下70mmまで除雪できる『確認車』を使用します。確認車による除雪後、さらにレール面下100mmまで除雪できる『ブラシ式除雪装置』、駅構内や本線上に積もった雪は『雪捨車』で定期的に排雪しています」(同)
新青森駅に到着した上り列車の着雪状況は、車両床下を撮影するカメラで確認して、対処が必要な際には、人力で対応しているそうです。
防雪柵は73.1km 運転計画も重要

JR北海道では、雪対策に「防雪柵」を設置しています。防雪柵には暴風雪や地吹雪による線路上の吹きだまりを防止する役目があり、これまでに函館線の江別〜豊幌間など、合計で73.1kmもの防雪柵が設置されているそうです。
また、荒天時に救護できない場所で長時間列車を停車させることのないよう、運転を取りやめる、運転本数を減らすなどして、状況に応じた運転計画を行っているといいます。
また、荒天時に救護できない場所で長時間列車を停車させることのないよう、運転を取りやめる、運転本数を減らすなどして、状況に応じた運転計画を行っているといいます。
雪害対策費の年間予算は50億円
JR北海道の雪害対策費は、年間で50億円にも上るそうです。年間の赤字総額が180億円という状況にあって、これは、本当に大変な負担ですね。しかし、そのお陰で、北海道人は日々無事に通勤・通学ができ、観光客も安心して冬の北海道を旅することができるわけです。
「最後は人力」というのも頭が下がるところです。JR北海道の皆さんに敬意を払いたいと思います。
「最後は人力」というのも頭が下がるところです。JR北海道の皆さんに敬意を払いたいと思います。