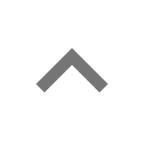12月〜2月で8割を占める
どのような状況で凍死するのでしょうか。論文「東京都における凍死症例の検討」(田中正敏ほか、1988年)によると、東京都監察医務院の記録では1978〜83年の5年間に都内の凍死症例が83件ありました。
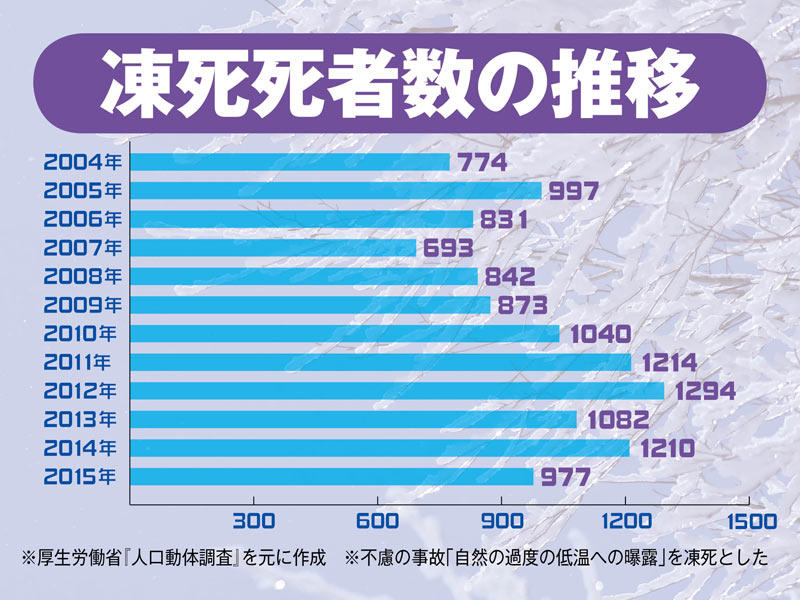
月別では12〜2月の3ヵ月で全体の77%、年齢では40〜50代が全体の63%、男女別では男性が89%を占めていました。発生状況をみると、屋外・屋内での酩酊状態が51%でもっとも多く、次いでホームレスが屋外で低体温症から凍死するケースでした。
気温11℃でも屋内で死亡例
死亡時刻を推定できる症例では、早朝5時台に発生が多く、午前3〜9時までの時間帯が全体の半数以上を占めていました。
死亡時刻前後の気温を調べると、ほとんどが11℃以下で、屋外では0〜5℃が多く、酩酊状態の場合は15〜19℃でも発生しています。一方、屋内での凍死は全体の25%ですが、死亡時の外気温は0〜11℃の範囲で幅広く分布していました。
屋内で凍死するケースは高齢者に多く、いわゆる「老人性低体温症」が原因と思われます。高齢者は暑さ、寒さに対する感覚が鈍くなります。通常は寒くなると皮膚の血流量が減少して体内の熱を逃がさないようにしますが、寒さを感じないと血流量が減らず、体が放熱を続けて体温が下がり、命を落とすのです。
死亡時刻前後の気温を調べると、ほとんどが11℃以下で、屋外では0〜5℃が多く、酩酊状態の場合は15〜19℃でも発生しています。一方、屋内での凍死は全体の25%ですが、死亡時の外気温は0〜11℃の範囲で幅広く分布していました。
屋内で凍死するケースは高齢者に多く、いわゆる「老人性低体温症」が原因と思われます。高齢者は暑さ、寒さに対する感覚が鈍くなります。通常は寒くなると皮膚の血流量が減少して体内の熱を逃がさないようにしますが、寒さを感じないと血流量が減らず、体が放熱を続けて体温が下がり、命を落とすのです。
低体温症の救急搬送の4分の3は屋内
日本救急医学会が2010年12月〜2011年2月の3ヵ月間に全国の救急医療機関を受診した低体温症の418例を集めました。凍死につながる低体温症の全国調査は初めてのことでした。
症例を分析すると、屋内で発症した人は全体の4分の3を占め、屋外発症の3倍にのぼりました。男女比は6対4、年齢は60歳以上が77%と高齢者が8割近くを占めていました。
残念ながら症例の約3割が亡くなりましたが、報告書は「冬季は基本的に室温を含め気温そのものが低いため、屋内であっても加齢、栄養状態の悪化や脱水、持病の悪化、体調不良を要因として簡単に低体温症に陥り、重症化を招きやすい」と指摘しています。
まだ寒い日が続きます。凍死しないために、泥酔して道端で寝ない、自宅を適切に暖房する、体調管理を怠らないといった簡単なことで命を守ってください。
症例を分析すると、屋内で発症した人は全体の4分の3を占め、屋外発症の3倍にのぼりました。男女比は6対4、年齢は60歳以上が77%と高齢者が8割近くを占めていました。
残念ながら症例の約3割が亡くなりましたが、報告書は「冬季は基本的に室温を含め気温そのものが低いため、屋内であっても加齢、栄養状態の悪化や脱水、持病の悪化、体調不良を要因として簡単に低体温症に陥り、重症化を招きやすい」と指摘しています。
まだ寒い日が続きます。凍死しないために、泥酔して道端で寝ない、自宅を適切に暖房する、体調管理を怠らないといった簡単なことで命を守ってください。