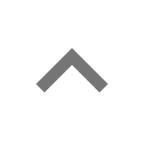両親はエドヒガンとオオシマ

ソメイヨシノとは、園芸用に2つの品種が掛け合わされた雑種です。ソメイヨシノをこの世に誕生させた両親は、エドヒガンザクラとオオシマザクラ。
この2つが自然交配によってできたのか、はたまた人工的に交配させてできたのかはわかっていません。ただ、江戸時代には園芸品種として確立したとされています。
この2つが自然交配によってできたのか、はたまた人工的に交配させてできたのかはわかっていません。ただ、江戸時代には園芸品種として確立したとされています。

ソメイヨシノはいいとこ取り!
そんなソメイヨシノをよく見てみると、満開時に葉はなく、花は大きめで見応え十分。これは、先程紹介した両親の良いところをうまく引き継いでいるのです。
オオシマザクラは葉と花が同時に出てきますが、エドヒガンザクラは花が咲いた後に葉が出ます。また、エドヒガンザクラの花弁は細長く小さめですが、オオシマザクラの花弁は大きめで丸みを帯びています。
いいとこどりなソメイヨシノは、まさに観賞用にぴったりな桜として人気を博したのです。
オオシマザクラは葉と花が同時に出てきますが、エドヒガンザクラは花が咲いた後に葉が出ます。また、エドヒガンザクラの花弁は細長く小さめですが、オオシマザクラの花弁は大きめで丸みを帯びています。
いいとこどりなソメイヨシノは、まさに観賞用にぴったりな桜として人気を博したのです。
どのソメイヨシノも遺伝子は同じ!?

人々の心を引きつけてやまないソメイヨシノは、少々厄介な面も持ち合わせています。それは自然に増えることが出来ないということ。
元からあった品種ではないですし、エドヒガンザクラとオオシマザクラを同じように交配させても、全く同じソメイヨシノを作ることは難しくなります。
「え!じゃあ日本全国にたくさんあるソメイヨシノはどうしてるの?」
あれは全てクローンなんです。
何もしなければせっかくのソメイヨシノも一代限りで衰退してしまう…!
ということで、遺伝子をそのままに繁殖させるべく、クローンが作られるようになりました。
元からあった品種ではないですし、エドヒガンザクラとオオシマザクラを同じように交配させても、全く同じソメイヨシノを作ることは難しくなります。
「え!じゃあ日本全国にたくさんあるソメイヨシノはどうしてるの?」
あれは全てクローンなんです。
何もしなければせっかくのソメイヨシノも一代限りで衰退してしまう…!
ということで、遺伝子をそのままに繁殖させるべく、クローンが作られるようになりました。
ソメイヨシノの繁殖方法

接ぎ木・挿し木・取り木について
ソメイヨシノのクローンは、以下の3つの方法で作られます。
【取り木】
増やしたい木の幹や枝の表皮をぐるっと切り取り、その部分に水苔を巻きつけます。十分な発根ができたら親株から切り離す。
【挿し木】
ソメイヨシノから切った若い枝を土に挿し、発根させて1本の木へと成長させる。
【接ぎ木】
オオシマザクラなど、土台となる木に切り込みを入れ、そこにソメイヨシノの若い枝を差し込んで合体させる。
※この場合、根はオオシマザクラですが、幹から上はソメイヨシノとなります。
実施されている割合的には挿し木が多いようです。
【取り木】
増やしたい木の幹や枝の表皮をぐるっと切り取り、その部分に水苔を巻きつけます。十分な発根ができたら親株から切り離す。
【挿し木】
ソメイヨシノから切った若い枝を土に挿し、発根させて1本の木へと成長させる。
【接ぎ木】
オオシマザクラなど、土台となる木に切り込みを入れ、そこにソメイヨシノの若い枝を差し込んで合体させる。
※この場合、根はオオシマザクラですが、幹から上はソメイヨシノとなります。
実施されている割合的には挿し木が多いようです。
クローン故のデメリット

美しい花を咲かせる優秀な遺伝子を、そのまま増やすことができるクローン桜。
しかし、そこにはデメリットもあったのです。
桜は「自家不和合性」という性質をもっています。なんとも難しそうな名前ですが、要は自分の花粉では受精しないということです。これには、自分の遺伝子を他の植物へ拡散する、あるいは他の個体の遺伝子を取り入れることで進化していく狙いがあるようです。
ソメイヨシノ以外の桜は、同じ品種であっても、別個体であれば遺伝子が異なるため、交配することが可能です。しかし、すべて同じ遺伝子のソメイヨシノは、この性質があるため、別個体と交配することが出来ないのです。もちろん、他の桜となら交配が可能ですが、それはもはやソメイヨシノとは別物になってしまいます。
また、もしも病害が広まった場合、それぞれ違った遺伝子をもつ桜たちであれば、病害に弱いものもいますが、強いものもいます。そのため全滅という被害は免れることができます。しかし、ソメイヨシノはすべて同じ遺伝子なので、病害が広がればすべてだめになってしまうのです。
しかし、そこにはデメリットもあったのです。
桜は「自家不和合性」という性質をもっています。なんとも難しそうな名前ですが、要は自分の花粉では受精しないということです。これには、自分の遺伝子を他の植物へ拡散する、あるいは他の個体の遺伝子を取り入れることで進化していく狙いがあるようです。
ソメイヨシノ以外の桜は、同じ品種であっても、別個体であれば遺伝子が異なるため、交配することが可能です。しかし、すべて同じ遺伝子のソメイヨシノは、この性質があるため、別個体と交配することが出来ないのです。もちろん、他の桜となら交配が可能ですが、それはもはやソメイヨシノとは別物になってしまいます。
また、もしも病害が広まった場合、それぞれ違った遺伝子をもつ桜たちであれば、病害に弱いものもいますが、強いものもいます。そのため全滅という被害は免れることができます。しかし、ソメイヨシノはすべて同じ遺伝子なので、病害が広がればすべてだめになってしまうのです。
人間とともに生きる

私たちが何気なく見ていたソメイヨシノは、自らその地の環境や気候に適応できるよう進化していくことが難しく、自然に繁殖することもできません。そのため、人間が気にかけてあげなければ衰退してしまいます。
「生涯人間の手が必要な桜」というと少し切ない気もしますが…「人間と共に生きる桜」と言い換えると、より身近で、より愛着がわく存在に感じませんか?
今年は、ソメイヨシノへの見方や接し方が少し変わるかもしれませんね。
「生涯人間の手が必要な桜」というと少し切ない気もしますが…「人間と共に生きる桜」と言い換えると、より身近で、より愛着がわく存在に感じませんか?
今年は、ソメイヨシノへの見方や接し方が少し変わるかもしれませんね。
参考資料など
【参考・参照元】
「さくら図鑑」roku-go.my.coocan.jp/hanamain/jumoku/sakura.htm
BotanyWEB「自家受粉と他家受粉」www.biol.tsukuba.ac.jp/~algae/BotanyWEB/self.html
「さくら図鑑」roku-go.my.coocan.jp/hanamain/jumoku/sakura.htm
BotanyWEB「自家受粉と他家受粉」www.biol.tsukuba.ac.jp/~algae/BotanyWEB/self.html